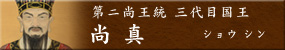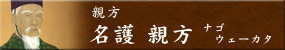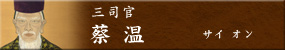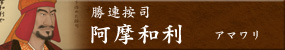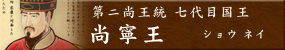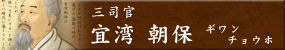牧志朝忠は中流士族の家に生まれ、21歳の時に北京に留学した。1840年、北京滞在中に阿片戦争目の当りにした朝忠は、清の衰退と列強の恐ろしさを肌で感じ、琉球にもやがて異国の知識と言語が必要になることを確信していた。 帰国後は英語話者安仁屋政補(あにやせいほ)に師事するなどして英語力を磨いた。朝忠が通訳官となった頃、琉球王府は相次いで訪れる欧米の商船や宣教師の対応に頭を抱えていた。琉球は薩摩の意向も伺いつつ策を講じるため、意思決定が非常に遅かった。しびれを切らし、時に武力をちらつかせて恫喝する欧米人に対しても理論的に対話し、博識で機転のきく朝忠は常に現場で必要とされ昼夜の別なく働き続けた。鎖国の時代に、彼はアメリカの政情にも明るく、ペリーを驚愕させたという。 朝忠の有能ぶりは、薩摩藩主で開明派の島津成彬(しまずなりあきら)から高く評価され、異例の大出世を遂げるが、皮肉な事に琉球内では妬みの標的にされてしまう。 順風満帆に見えた人生は成彬のの急死により一変、対立派により反逆罪の嫌疑をかけられ、親薩摩派とされた人々は投獄され死者が出る程凄惨な拷問が行われた。薩摩は彼を通訳官として召し抱えたいと獄中の身柄を奪取するが、上国の途上、彼は船から身を投げてしまったという。一躍時代の寵児となるような、活躍の場が開けた所での謎に満ちた急死であった。
「この青年は教育を受けた琉球の人々によくみかけるのとは違ってもっと浅黒い顔色をしていたし、また、その眼は黒く鋭く、俊敏で油断のない顔付きをしていた」 ブロッサム号来琉記より
「初め朝忠 仏人に対し条約を拒否するや、提督勃然(ぼつぜん)として怒り、将士をして剣を抜いて之れに逼(せま)らしむるも恐怖の色なく、之を諭すに理を以てす。将士※莞爾(かんじ)として剣を飲む」 東汀随筆・続編より
※にっこりと微笑むさま